



「上手(じょうず)は下手(へた)の手本なり、下手は上手の手本なり」。私はこの世阿弥(ぜあみ)の名句をとても気に入っています。
上手とは、知識経験や技術力において、一般的な水準よりも立場が上であったり、優れている人のことを指します。下手が上手をお手本にして学ぶのは、容易に理解できます。下手を弟子とし、上手を師匠とすると、実に論旨が明快です。弟子が師匠を手本にして学ぶ、ということは、至極当然といえるからです。
下手をアマ、上手をプロとしたり、下手を部下、上手を上司と解釈してもいいでしょう。ところが、「下手は上手の手本なり」の真の意味はどういうことでしょうか。恥ずかしながら、学生時代にこの言葉を聞いたとき、妙な違和感を感じたことを鮮明に覚えています。師匠は弟子を、上司は部下を、プロはアマを手本にすべきだということになり、その真意がまったくわからなかったからです。
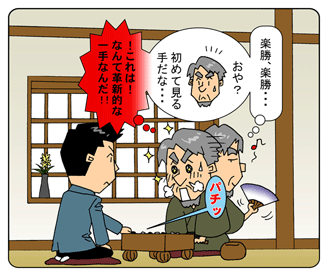
たとえば、将棋という勝負の世界で考えてみましょう。将棋界において上手(うわて)とは、相対比較して相手よりも強い人、下手(したて)とは弱い人を意味します。
強さや実力を客観的に表すために、アマチュアもプロも、日本将棋連盟が段級位制を採用しています。アマチュアの場合「級位」は、十級からはじまります。強くなるにしたがって、九級、八級、七級…と数字が下がっていきますが、反対に「段位」は、初段、二段、三段と逆に、数字が上がっていきます。
一級と三級では、三級の方が下手であり、初段と三段では、三段の方が上手になるのです。
昔から、アマとプロの実力の差がもっともかけ離れている競技のひとつが、将棋といわれています。アマからみると、プロは神様のような絶対的な存在です。かつてプロを目指していた元奨励会員やアマ棋戦の全国大会優勝の常連組以外、一般的にアマがプロに勝つことはまずありえません。
そんなレベルの違いが歴然と存在する厳しい勝負の世界において、アマがプロを手本にするのは当然のこととしても、プロがアマをお手本とするようなことが、果たしてほんとうにあるのか、と疑問を抱いたのです。さっそく、知人の将棋のプロ棋士に尋ねてみることにしました。すると、これが意外と少なくないというのです。
現在流行している戦法の多くは、ひと昔前では考えられなかったような型ばかりで、なんと、それらはアマチュアの人が考案したものが少なくないというではありませんか。
この事実には、驚愕しました。定跡(プロ棋士たちにより長年研究された、ある局面で最善手とされる攻めや受けの手筋などの集大成)にとらわれないアマチュアならではの柔軟な視点・発想から、斬新でユニークな戦法が生まれているというのです。
ややもすると、上手が陥りやすいのは、自分よりも仕事の能力の低い人や未熟な者からは何も学ぶことがないという「おごり」です。「おごり」とは、うぬぼれであり、思い上がりです。おごりが油断を生むのです。
油断、すなわち、ちょっとした気の緩みがその後の大惨事を招きます。自分で自分のことを完璧だと思った瞬間から、人は退化がはじまります。自分以外のすべての人に対して、だれであっても、自分にとってのお師匠さんと思うべしという意味です。
相手が年上であろうが年下であろうが、上手であろうが下手であろうが、自分より優れている魅力があったり、見習うべき点があったり、その人から学ぶべき点は必ず存在するはずです。
もし、あなたの周囲や身近な人に対して、あなたが見習うべき点がひとつもないということを本気で思っているのなら、大問題です。あなたの心の中にすでに「おごり」が宿っているということになります。「下手は上手の手本なり」とは、上手の「おごり」を戒めした言葉だといえるのです。
自分が「下手」であることを客観視している期間はいいのですが、自他ともに「上手」の領域に近づけば近づくほど、「おごり」という邪悪な心が宿りやすくなります。
私こそこの道の第一人者、社内で私が一番詳しいという「おごり」がふつふつと芽生えはじめると、下手や年下の人間からは、なかなか素直に吸収することができにくくなるものです。常に「おごり」を排除することを意識し、年下であろうが、下手であろうが、相手がだれであろうとも、謙虚に学ぼうとする姿勢が大切なのです。
四十歳という年齢がひとつの大きな節目の年齢だと思っています。四十歳までは上手から、四十歳を超えると下手から、学ぶことを意識すべきだと常々私はいっています。孔子でいうところの「不惑(ふわく)」以上になると、意識して新しいテクノロジーやトレンドを能動的につかもうとしなければ、感性がにぶり、時流についていけなくなる危険性があるからです。
「下手は上手の手本なり」の真意を理解してからというものの、自分よりもスピーチが上手な人はもとより、あまり話が上手くない人を参考にすることも積極的に心掛けるようになりました。
私は人前で話すことが多い職業です。たとえば、結婚式の披露宴などでは、とくに話下手の来賓のスピーチを注視し観察します。このことはけっして、相手を見下したり、軽んじたりしているわけではありません。「なぜ、つまらないのか」「なぜ、眠気を催すのか」など、話がうまくない人の特徴や話の構成をつぶさに研究することで、新たな発見や気づきが得られたり、初心に立ち返ったりすることができるからです。
上司の立場で考えるなら、不器用な人やできない人の目線に立つことが非常に重要だということです。部下を育てるのは、苦悩でもあり、喜楽でもあります。
なぜいつまでたっても部下が未熟なままでいるのか、なぜ部下に任せるといっこうに仕事が進まないのか、部下の成長が遅いのは、指導を受ける側ではなく、指導する側の問題である場合が多いということを示唆しています。部下は上司の姿を映す鏡です。教えることは、教わることです。
私自身、上司として指導の至らなさに愕然とさせられ、猛省することばかりです。自らの教え方・指導法がまずいから、部下がいっこうに育たない、と自分の未熟さを思い知らされるのです。この気づきこそ、下手が上手のお手本といわれる所以でしょう。
上手もまた下手の失敗や不手際などを参考にして、自分の指導法を省みたり、芸の幅を広げたりする必要があるのです。部下とは修業の相手であり、ときとして「弟子」にも、「師」にもなるのです。
齢を重ねるにつれ、また知識経験を多く積むにつれ、かえって、そのこと自体が自らの成長・進化の阻害要因となることがあります。従来の固定概念や過去の成功体験に、人は無意識的に縛られるからです。いったんオールクリアのリセットボタンを押し、知識や経験値から考えるのではなく、ゼロベースでまっさらな頭にして、考えることが大事です。
自分の仕事を「朝飯前だ」とか「目をつむってでもできる」と思っているようでは、実はまだまだ仕事の本質を「わかっていない」ものです。 仕事が何であれ、極めようとすれば奥は深いものです。「わかった」つもりになることが一番危険です。それゆえ、自分はまだまだ「未熟」「わかっていない」を念頭に置いて、仕事に取り組むべきです。
経験を積めば積むほど、人の意見に謙虚に耳を傾けることができる人が、ほんとうの上手といえるのです。「上手は下手の手本なり、下手は上手の手本なり」とは、ほんとうに感慨深い言葉であり、「我以外皆我師」(われいがいみなわがし)に通じるものだと私は解釈しています。我以外に、下っ端も、上もないのです。







